
映画『花束みたいな恋をした』をご覧になり、主人公の麦と絹が共通の趣味で意気投合する様子に心を打たれた方も多いのではないでしょうか。
二人の感性を象徴するように、本棚にある本や、互いに好きな作家、そして会話の中に登場する漫画 宝石の国などの多種多様な作品が劇中に出てくる本は、映画の重要な要素として描かれています。
この記事では、なぜ二人の本棚が「ほぼ同じ」だったのか、そして二人の関係性の変化とともに本棚の中身がどのように変わっていったのかを詳しく解説します。
この記事でわかること
- 映画に登場するキーとなる作家や作品
- 主人公二人の本棚に並んだ具体的な作品名
- サブカルチャーが二人の関係にどう影響したか
- 時間の経過とともに変化する本棚の意味
『花束みたいな恋をした 』二人の本棚とサブカルチャーを徹底解説
- 絹と麦の好きな作家から探る共通の感性
- 映画のキーアイテムとなる今村夏子のピクニック
- 麦と絹の本棚にある本と漫画
- 特に意識した漫画 宝石の国
- 物語を彩るサブカルチャーの数々
絹と麦の好きな作家から探る共通の感性

主人公の絹と麦が初めて出会った夜、二人はお互いのリュックから読みかけの文庫本を取り出し、互いに好きな作家がほとんど同じであることに驚きます。
このシーンは、二人の恋が始まる上で非常に重要な意味を持っています。
文庫本の栞が映画の半券であることも含め、彼らがカルチャー全般を深く愛していることが伝わる名場面です。
二人が語り合った好きな作家は、以下の通りです。
- 穂村弘
- 長嶋有
- いしいしんじ
- 堀江敏幸
- 柴崎友香
- 小山田浩子
- 今村夏子
- 小川洋子
- 多和田葉子
- 舞城王太郎
- 佐藤亜紀
- 野田サトル
- ほしよりこ
- 市川春子
- 滝口悠生
- 小川哲
- 近藤聡乃
- 西村ツチカ
これらの作家に共通するのは、純文学やサブカルチャーの枠に収まらない、独自の作風を持った人々だという点です。
また、多くの作品が文庫化されていることから、書店で手軽に手に取れる身近な存在であったことも推測できます。
二人はそれぞれの作家への深い愛を語り、言葉を交わすだけで心が通じ合うような感覚を覚えたことでしょう。
このように、二人の間に共通の作家が存在したことは、単なる趣味の一致ではなく、お互いの価値観や感性が似ていることを示す「運命的な出会い」として描かれています。
ただ単に本を読んでいるだけでなく、作品の持つ世界観や著者の思想まで共感できる相手は、そう簡単には見つからないからです。
今更、花束みたいな恋をしたを観たけれど坂元裕二節炸裂!感想は色々あれど、こういう大きな本棚のある家で、可愛い猫と一緒に時の流れを気にすることなく暮らしたいなあと思った。主演2人の演技は必見。 pic.twitter.com/OA2JT5ASpU
— ko (@dora_yaki_oishi) September 19, 2023
映画のキーアイテムとなる今村夏子のピクニック
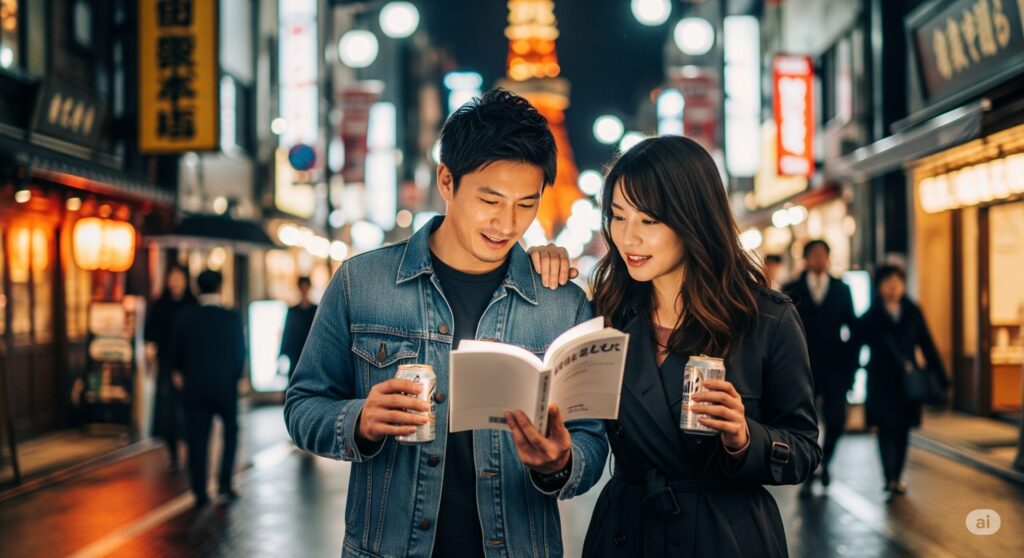
映画の冒頭、麦と絹は缶ビールを片手に夜道を歩きながら、今村夏子さんの作品について語り合います。
特に、デビュー作『こちらあみ子』に収録されている短編小説「ピクニック」を絶賛するシーンは印象的です。
この「ピクニック」という作品は、その後二人の関係性を示す上で重要なキーワードとなっていきます。
物語の中盤、就職活動に苦戦する絹が圧迫面接で理不尽な質問をされた際、麦は「その人は、きっと今村夏子さんのピクニック読んでも何も感じない人だ」と絹を慰めます。
この言葉は、二人の感性の指標であり、共通の敵に対する連帯感を生み出しました。
しかし、時間が経ち、二人の関係がすれ違っていく中で、再びこのフレーズが登場します。
今度は麦が口にしたその言葉に、絹は以前のような共感を感じることができず、二人の心の距離が遠ざかっていることを痛感するのです。
「ピクニック」は、ある女性の語りから始まる不思議な物語です。
日常の中に潜む不穏な空気や、人々の心の奥底にある奇妙な感情を描いており、読み手によって様々な解釈ができる作品として知られています。
二人がこの作品に共感できたことは、世の中の表層的な部分だけでなく、その奥にある複雑な感情や違和感に気づける感受性を持っていることを示しています。
また日本帰ってマッチングアプリで出会った🚹と居酒屋デートした後おもむろに手を繋がれ「これからどうしよっか♪」と言われた時にそのまま2件目行って好きな作家の本交換しあってカラオケ行ってキノコ帝国歌って彼の部屋の本棚見て「ほぼうちの本棚じゃん」で始まる花束みたいな恋がしたい。 pic.twitter.com/R9ZGcJa4vs
— ひつじちゃん🐏🇬🇧 (@__Hitsujichan__) February 23, 2023
麦と絹の本棚にある本と漫画

麦の部屋を訪れた絹が「ほぼ、うちの本棚じゃん」と驚くシーンは、二人がいかに趣味が似ているかを象徴しています。
本棚に並んだ作品は、二人の自己紹介であり、お互いの知らなかった部分を深く知るきっかけとなりました。
二人の本棚に共通して並んでいた作品と、同棲を始めてから加わった作品は以下の通りです。
二人の本棚に共通して並んでいた作品
- 小説:朝井リョウ『何者』、阿佐田哲也『麻雀放浪記』、奥田英朗『イン・ザ・プール』、カート・ヴォネガット・ジュニア『タイタンの妖女』、角田光代『空中庭園』、杉浦日向子『東のエデン』、フィリップ・K・ディック『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』、三浦しをん『まほろ駅前多田便利軒』、宮沢賢治『童話集 銀河鉄道の夜 他十四篇』、村上春樹『海辺のカフカ』
- 漫画:荒木飛呂彦『ジョジョの奇妙な冒険』、ジョージ朝倉『溺れるナイフ』、手塚治虫『アドルフに告ぐ』、花沢健吾『アイアムアヒーロー』、藤子・F・不二雄『異色短編集 ミノタウロスの皿』、松本大洋『青い春』
- 写真集・その他:梅佳代『じいちゃんさま』、川島小鳥『未来ちゃん』、中野正貴『TOKYO NOBODY』、旅行ガイドブック『地球の歩き方』
同棲を始めてから加わった作品
- 大友克洋『AKIRA』
- 三浦しをん『あの家に暮らす四人の女』
- 高野文子『黄色い本』
- 佐藤亜紀『醜聞の作法』
- 円城塔『これはペンです』
- 柴崎友香『ビリジアン』
- 近藤聡乃『A子さんの恋人』
- 森見登美彦『夜は短し恋せよ乙女』
- 町田康『屈辱ポンチ』
- 西加奈子『しずく』
- 舞城王太郎『イキルキス』
- 長嶋有『佐渡の三人』
- 森博嗣『数奇にして模型』
これらのリストは、二人の読書傾向や共通の関心事が時間を経てさらに深まっていったことを示しています。
『花束みたいな恋をした』血吐きながら観た。趣味で繋がった2人が趣味で離れるという流れの話。相手の本棚眺めるのはほぼセックスやろがい。深夜営業のファミレス、間違えて来たパフェをもらってスマホ越しの「付き合って下さい」は神がかっていて…私達あの時の気持ち簡単に忘れちゃうんだね。 pic.twitter.com/nM7INEygJ6
— れんげちゃん (@rennge_nekokai) May 19, 2024
特に意識した漫画 宝石の国

市川春子さんの『宝石の国』は、二人の甘い同棲生活を象徴する作品として描かれています。
ベッドの上でお菓子を食べながら、一つの漫画を二人で読んで涙を流すシーンは、同じ作品で同じように心が動くという、幸せな日常の一コマを鮮やかに切り取っています。
『宝石の国』は、宝石の体を持つ生命体たちの戦いを描いた独特の世界観を持つ漫画です。
この作品は、アニメ化もされており、多くのファンを持つ人気作です。多くのファンを持つ漫画でありながら、物語のテーマが深く、単なるエンターテインメントを超えた文学的な要素も持ち合わせています。
このような作品を共有できたことは、二人の関係が表面的ではない、深い部分で繋がっていたことを示しています。
もちろん、二人が楽しんだのは『宝石の国』だけではありません。
同棲を始めたばかりの頃に発売された野田サトルさんの『ゴールデンカムイ』も、二人の恋の始まりから終わりまでを見守る重要な作品です。
特に、麦が仕事に追われて7巻で読むのをやめてしまう一方で、絹は13巻まで読み進めているという描写は、二人の心の距離が広がっていることを示唆しています。
麦と絹の漫画の好みには、少年漫画のようなメジャーな作品から、独特な世界観を持つサブカル的な作品まで幅広く含まれています。
ただ、人気漫画でも『ワンピース』のような超メジャーな作品ではなく、『ゴールデンカムイ』や『宝石の国』といった、少し通好みの作品を選んでいるところが、二人のこだわりを感じさせます。
物語を彩るサブカルチャーの数々

『花束みたいな恋をした』は、書籍だけでなく、映画、音楽、演劇、ゲームなど、様々なジャンルのサブカルチャーが物語を彩っています。
これらの固有名詞の羅列は、単なる背景ではなく、二人の人間性や時代の空気感を表現する重要な役割を果たしています。
二人が出会ったきっかけの一つも、押井守監督らしき人物を喫茶店で見かけたことでした。
映画の序盤では、二人がカラオケで歌う曲も、人気アーティストの代表曲ではなく、きのこ帝国の『クロノスタシス』やフレンズの『NIGHT TOWN』など、当時のサブカル好きに刺さる選曲でした。
この選曲は、二人が単に流行に乗るのではなく、自分たちの好きなものを追求するタイプであることを示しています。
また、同棲生活では『ゼルダの伝説』のゲームを一緒に楽しむ様子も描かれました。
しかし、麦が仕事に追われ、ゲームに費やす時間がなくなり、絹だけがゲームを続けるという描写も、二人の関係性の変化を物語っています。
このように、様々なサブカルチャーが物語に登場することで、二人の恋愛が単なるフィクションではなく、多くの人が経験するであろう「リアルな恋」として描かれています。
特に、好きなものが共通しているという理由で意気投合し、恋に落ちるという展開は、多くのサブカル好きの共感を呼ぶ大きな要因となりました。
これは、サブカルが単なる趣味ではなく、個人のアイデンティティを形成する重要な要素であることを示していると言えるでしょう。
『ファーストキス』とか、『花束みたいな恋をした』とかに出てくる、リビングに本棚で壁みたいにして区切るやついいよね。
— 陸のOLゆらゆた🐸船とバイクと猫が好き (@yurayuta3126) May 5, 2025
完全に壁じゃなくて、本棚で少し向こう側が見えるやつ。 pic.twitter.com/48mDkkG1mi
『花束みたいな恋をした 』本棚から読み解く二人の変化
- 二人の会話に登場する劇中に出てくる本
- 変わっていく麦と本棚に残るサブカル
- 麦が読み始める自己啓発本とは
- 好きなものとどう向き合うかという問題
- 本棚とサブカルから紐解く二人の感性と変化:まとめ
二人の会話に登場する劇中に出てくる本

前述の通り、映画『花束みたいな恋をした』には、二人の本棚に並んでいる作品以外にも、会話の中に多くの書籍が登場します。
特に印象的なのは、滝口悠生さんの『茄子の輝き』です。
この作品は、絹が「すごくよかった」と絶賛し、麦に薦めるも、忙しさから読む時間がない麦によって積読の山に追いやられてしまうというシーンで登場します。
これは、二人のライフスタイルや価値観が少しずつずれていく様子を象徴しています。
麦と絹が出会った頃は、お互いに好きな本を積極的に勧め合い、感想を共有していました。
しかし、社会人となり、それぞれの生活環境が変わっていく中で、その機会は減っていきます。
同じものを読んで、同じように感動するという共通の体験が失われていくことが、二人の心の距離を広げる一因となったのです。
二人のすれ違いは、どちらか一方が悪いというわけではありません。
麦はイラストレーターの夢を諦め、生活のために仕事に邁進しました。一方、絹は自分の好きなものを大切にする生き方を選びました。
これは、誰もが直面する可能性のある「人生の選択」であり、多くの観客がどちらの気持ちにも共感できるポイントだと言えます。
「花束みたいな恋をした」の麦と絹ちゃんが同棲をする部屋は、サブカル好きの2人の好きなものがギュッと詰まっているのが伝わってくるので大好き#花束みたいな恋をした pic.twitter.com/Us22JEY80V
— 𝘺𝘰𝘭𝘪𝘤𝘦 (@yolice_221B) January 10, 2025
変わっていく麦と本棚に残るサブカル
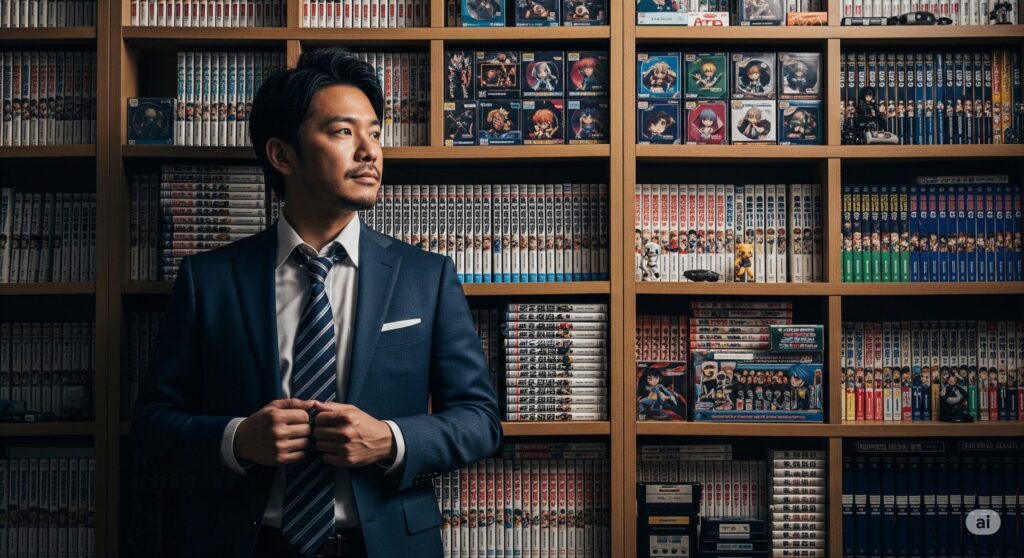
麦が会社員として働くようになってから、彼の本棚は少しずつ変化していきます。
かつて二人が愛した小説や漫画は、依然として本棚にありますが、麦が読むものは変わってしまいました。これは、麦の価値観が変化したことを示しています。
麦は仕事にやりがいを感じ始める一方で、昔のようにサブカルに没頭する時間がなくなっていきます。
かつては「人生の楽しみ」だったサブカルが、いつの間にか「学生時代の思い出」になってしまったのです。
これは、多くの人が経験する現実であり、映画が共感を呼ぶ理由の一つです。
本棚に残されたサブカル作品は、かつての麦と絹の関係性を思い出させると同時に、現在の麦と絹の間に横たわる隔たりを浮き彫りにしています。
麦にとっては、仕事で疲れた体でサブカル作品と向き合うことが難しくなり、より手軽で現実的なエンターテインメントへと興味がシフトしていったのかもしれません。
この変化は、麦が「成熟」したと捉えることもできるでしょう。しかし、絹から見れば、それは「変わってしまった」ことに他なりません。
同じものに感動し、同じように楽しむことができなくなった二人の間には、大きな溝が生まれてしまったのです。
麦が読み始める自己啓発本とは
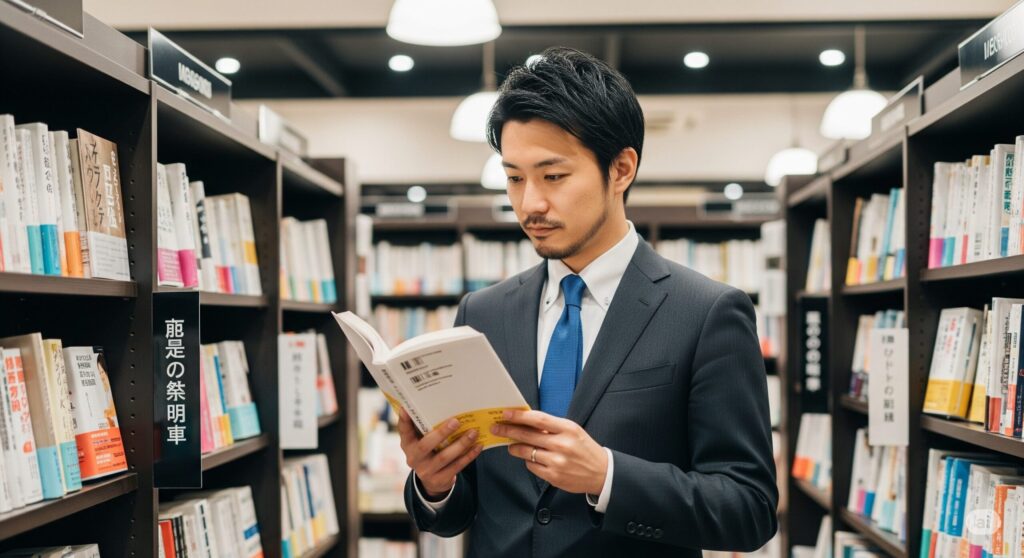
仕事に追われるようになった麦が、書店で立ち読みしていたのは前田裕二さんの『人生の勝算』という自己啓発本でした。
この作品は、ライブ配信サービス「SHOWROOM」を創業した前田氏が、自身の半生やビジネスへの考え方を綴ったベストセラーです。
麦がこのような本を手に取るようになったことは、彼の価値観が大きく変化したことを象徴しています。
麦は、かつてはアートや文学といったサブカルチャーを愛し、「お金よりも感性」を重視するタイプでした。
しかし、社会に出て現実の厳しさを知る中で、彼はビジネスや自己成長といったより「現実的な価値」を求めるようになったのです。
この変化は、二人の関係性にも大きな影響を与えます。
絹が楽しそうにサブカルの話をしても、麦は上の空で聞き流すようになり、二人の会話は徐々に減っていきました。
自己啓発本を読み始めた麦は、もはや学生時代とは別人でした。
| 学生時代 | 社会人になってから | |
|---|---|---|
| 趣味 | サブカルチャー(映画、小説、漫画) | 仕事、ビジネス書 |
| 価値観 | 感性、共感、楽しさ | 成果、現実、成長 |
| 口癖 | 「やっちゃえよ」 | 「今度話すから」 |
このように、麦の価値観の変化が本棚や彼の言動に明確に表れることで、二人のすれ違いがよりリアルに感じられるようになっています。
好きなものとどう向き合うかという問題
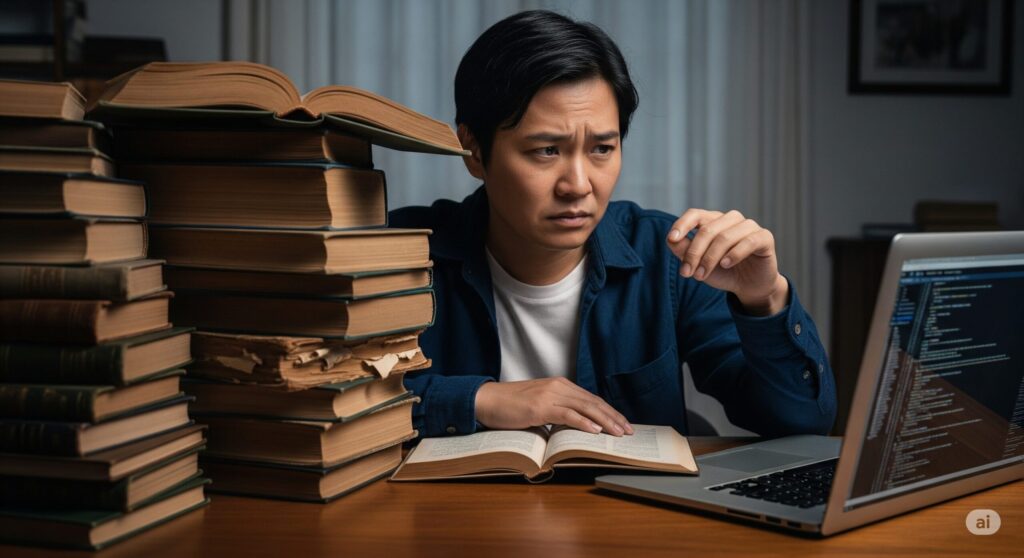
映画『花束みたいな恋をした』は、ただの恋愛映画ではなく、好きなものとどう向き合うかという普遍的なテーマを投げかけています。
麦と絹は、好きなものが同じという共通点から恋に落ちましたが、その「好きなもの」との向き合い方が変わったことで、関係が破綻してしまいます。
学生時代の二人は、好きなものに没頭する時間があり、それを共有することで喜びを感じていました。
しかし、社会人となり、麦は生活のために好きなものを犠牲にし、仕事に打ち込む道を選びます。
一方、絹は好きなものを大切にする生き方を貫きました。どちらの選択が正しかったか、という問いに明確な答えはありません。
この映画は、人生の様々な選択の中で、自分の好きなものとどう折り合いをつけていくのか、という難しい問題を私たちに問いかけているのです。
多くの人は、多かれ少なかれ、麦のように現実と向き合い、好きなものを諦めたり、後回しにしたりする経験があります。
だからこそ、多くの観客が麦にも絹にも感情移入し、二人の結末に胸を締め付けられるのです。
この映画は、恋愛の物語であると同時に、誰もが直面するかもしれない人生の岐路を描いた物語だと言えるでしょう。
本棚とサブカルから紐解く二人の感性と変化:まとめ
映画『花束みたいな恋をした』が多くの観客を魅了した理由は、単なる恋愛模様だけでなく、本棚やサブカルチャーを通して描かれるリアルな人間ドラマにあります。
この記事を通して、改めて二人の関係性や価値観の変化について理解を深めていただけたのではないでしょうか。以下に、記事の要点をまとめます。
最後までお読みいただきありがとうございました。